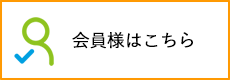玄信流 篠笛、横笛教室 八王子「竹の音會」は東京八王子、立川、多摩、日野近くでのレッスン、出張レッスンを行っております。オンラインレッスンもございます。
笛の心 和の音 先人の語録集
篠笛奏者 福原百之助 語録
一本の絹糸がしなやかにのびるような切れ目なく流れるような吹き方によって曲全体にまとまりとまろやかさを付加することが大切になります。
呼吸法の会得が笛方の修練すべき事柄だとされるのもそのためです。
「切れ目なく流れるように吹く」とは、とりもなおさずまず息をできるだけ長く持続させることにほかなりませんから。
笛方が必ず腹で深く息をする腹式呼吸を行い、また武道と同様「臍下丹田に気息を集め、力をこめよ」などと訓えられるのもそのためです。
しかし人体の呼吸にはたとえばいくらたくさん息を吸い込んでおこうと努めたところで呼吸循環器系の許容量には限界があります。
そこで笛方ならではの課題として重視されるのが「息つぎ」ということになるのです。いかにタイミングよく「息つぎ」を調節しいかに聴衆に気づかせぬ「息つぎ」を行うかが問題になるわけです。
「唄をうたうように笛を吹くように」
それまでの笛の世界では先人が脳裏に得た曲想を笛に託して推敲しながら曲として定着させたいわば”聴譜”とでもいうべきものを稽古時や発表会などを通じて相手の聴覚や大脳に灼きつけるといった伝授伝承のやり方だけが慣用されてきておりました。
このやり方は稽古の積み重ねをまってはじめて可能となるものだけに修行という意味では必ずしも悪くはありません。
精神集中力が培われますし師弟の人間対人間のこころの結びつきが強められまた体得し血肉化されることによって一生絶対に忘れられないものとなるであろうからです。
ただこのやり方ですと伝授する側・伝承する側の資質や恣意や感受性、理解力や解釈力や記憶力によっては原曲が誤って伝えられたり歪められたりへたをすると次第に異質の曲に改変され改善ならまだしも改悪される惧れも生じかねません。
またマン・ツー・マンは結構なのですがこれですと限られた師弟の範囲でしか学習できず地域的あるいは時間的にそうした機会に恵まれない独習者とりわけ初心者はせっかくの意欲をくじかれてしまいましょう。
自分で笛の曲を創作したいと思う方にとってもどのような形で表現すればよいのか困惑されるはずです。
十代、二十代の若手のうちは吹く笛の音色や音調にどこかういういしさやみずみずしさが感じられる反面お師匠さんから手ほどきされたやり方を踏襲している段階では本人ならではの個性が音になっては出てきません。
「学ぶ」の語源は「真似ぶ」つまり真似することからきているということですが学ぶ・真似ぶうちはどうしても型通り忠実に吹こうと努めるあまりぎこちなく今ひとつ伸びやかさに欠けがちです。
それが三十代、四十代、五十代と試行錯誤を繰り返しながら齢を重ねてまいりますと”自分の笛の音”を自分で聴き取り、聴き分けられるようになりより良い音を出す工夫をするうち自然に自分の個性が磨き出されてきます。
そして六十代、七十代と人生経験を積み物の見方や考え方が円熟の境地に入れば入るほど全人格が笛の音に託され自在の至境にまで達するわけです。
私はそうした至境には少なくとも七十歳を過ぎなければ到達できないのではないかという気がしてなりません。そしてこのことは絵の世界にも共通しているようです。
四十代に入ってから突然、私を見舞ったスランプは約十年もの間つきまとって離れない深刻なものでした。笛がどうしても思うように鳴らなくなってしまったのです。
私の場合スランプは文字通り”ある日突然”起きました。
舞台で吹いている最中、不意に音がかすれしまいには「スースー」という息の音だけになってしまったのです。
やむなくいったん笛を口許から離し、唇を湿らせ気を取り直して再び吹きはじめてみますと最初はいくぶん笛の音になったのですがものの三十秒と立たぬうちまたもや音がかすれて出なくなりました。周章狼狽とはあの時の心理状態です。
あとはもう必死で笛に息を吹き込み鳴っているのやら鳴っていないものやらお構いなしにとにかく悪夢のような舞台をつとめ終えました。
しかも「鳴らない笛」はその日限りではなかったのです。来る日も来る日も全く同じ状態の繰り返しという悲惨きわまる事態に立ち至ったのです。
私は四十代という本来なら最も脂がのって然るべき時期に思いもかけず原因不明の”奇病”に取り憑かれてしまったわけです。
演奏家にとっては致命傷ともいえる”奇病”との悪戦苦闘の日々が始まりました。
結局私の長いスランプは自分で自分を必要以上に難しいところまで追いつめた意識過剰が引き金となった俗に言う「自縄自縛」的なストレス現象だったのかもしれません。
そのため平常心を見失い焦れば焦るほど泥沼に足がはまっていたのでしょう。
五十一歳不惑の齢にかえって惑いが生じてから足掛け十一年目の土壇場での開眼で改めてつくづく考えさせられることですが笛を吹くにあたって最も大切なポイント要諦は「平常心」なのではないでしょうか。
「平常心」とは詠んで字のごとく「平生の常なる心」であり人間がこの世に生を享けてから先ずっと臨終の瞬間まで途絶えることなくふだんは別に意識せず息を吸い息を吐く呼吸のように意識することなく自分なりのありのままの自然体で振る舞う心の持ちようを指すのでしょう。
私はこれを私なりに素の「真白な心」と解し美しい笛の音色というものは吹き手がその「真白な心」で笛に接し得たとき初めておのずから流露する純粋で清澄な音の色であると信じております。
喜怒哀楽の感情を持つ人間はそれが人間臭さをもたらすとも言えましょうがいずれにしてもたとえば心が怒っている時には怒っているような言葉つきとなり哀しい心から発せられる言葉は自然に哀しい気になります。
笛はそれと同様の理で息を媒体として心のありようを具現化いたします。
すなわち心が怒れば怒った音色、心が哀しければ哀しい音色となり要するにそこに少しでも「私」情がはたらいて心が乱れると音色も乱れたちまち濁った音色が出てしまうものです。
~嘘・偽りの術を知らぬ一管の自然の産物~
篠竹は人間の言葉以上に真正直な性格を有するものですからその真正直さゆえに演奏者にとってはその時その時の心の襞まで映し出されてしまういわば照魔鏡ともなり、諸刃の剣ともなります。
私が、理想の笛の音色は吹き方が喜怒哀楽の私道を越えて篠竹一管に「真白な心」の「平常心」を託すとき初めて流露すると述べたのはつまりその極致で篠竹一管の真正直な性格自体が生かされるという意味です。
人間が「真白な心」になり切った境地は「祈り」と称してよいのではないか、と私は思います。
手前勝手な神頼み、仏頼みの”願いごと”ではなく己の力の限界を悟った者が己の力を超えた大いなる存在としての神仏に己の”いのち”を委ねるという純粋な「祈り」と称しても、です。
私は長いこと、みずからの”いのち”言い換えれば生命力や精神力を高めたく神仏に「祈り」を捧げるつもりで笛を吹いてまいりました。
宗教というものが宗派や教団の別を問わず究極はみな神仏あるいは天に祈る心のすすめだとするならば私にとって笛は宗教そのものであったと申してさしつかえありません。
それもこれもすべては笛の吹き手としての運命に生きる者として笛の要諦が「平常心」の「真白な心」にあるとの私なりの結論に達したがゆえでした。
そのことと多少関連するかもしれませんが私は、若い時分から演奏中には「目は半眼、四肢身体の動作は最小限にとどめる」
といういわゆる禅定の構えを心がけることに努めてきたつもりです。禅定とは座禅によって精神を丹田に集中統一し、忘我の浄域に三昧することです。
こう解説すると何か固苦しい感じになりますが実際にはこの構えほど座法としては自然体に近いものはありません。
「半眼」にするのはあくまで「静」的に己の内的宇宙を形づくっていこうとする日本音楽特有の哲理にはそれが最適であろうと信じるからです。
また「最小限の動き」も同じように日本音楽特有の哲理を具現化するためにはそう心がけることが大切だと信じるからです。
笛を吹くにあたり「平常心」とともに大事な心がけ、基本的姿勢の一つは「笛に対し、曲に対して素直になること」ではないでしょうか。
虚心坦懐と申しますか何のわだかまりもなく素直に明るく接することが笛を生かし曲を生かす必須条件だと思うのです。
笛という真正直な性格の楽器には賢しげな小細工や見てくれの技巧などは不必要、いや禁物です。
指を速く動かせるとか、メリカリがうまいとかいったことは修練の結果としてもたらされる種類の事柄であっていわば笛を吹くうえでの付随的産物に過ぎず決して笛の道における本質的な存在理由ではありません。
あくまで「修練の結果」として評価されるべきであって最初からそれを狙い、それを策するようないわゆる技巧派の笛は聴き手の耳をくすぐることはあっても感動や充足感や陶酔の歓びを喚起することはありますまい。
「仏作って魂入れず」のことわざではありませんがいくら技術的には優れた才能を発揮できる笛吹きでもそこには純心無垢な「祈り心」の魂がこめられていなければ笛としては一流たり得ません。
そしてその「魂」こそ「素直さ」の結晶にほかならないと思うのです。
「素直さ」の価値はたとえば前記のように吹き手自身に精神的な安定感をもたらすこと篠笛という自然の植物から作られた楽器の真正直な性格を生かすことその他いろいろ考えられますが次に一つの例として「曲に対する素直な心の価値」について少しばかり記させていただいたことにします。
まず結論から先に申しますと曲に対して素直な心をもって接することは曲想全般にわたってその意図するところの真意を正しく把握させますしその背景や土台の上に展開される”音のドラマ”の登場人物の心情や出来事の機微を理解するのに役立ちます。
と言うことを要約しますとつまり「素直な心」は「曲に感情移入する」最善の前提条件であるわけです。
その「感情移入」を可能とするものはまず豊かな人生経験でありその人生経験も触れ合う人と人との関わりに根ざしたものでなければなりませんでしょう。
喜怒哀楽の情、優しさ、思いやりの心を知り、培うためにです。そして究極は前に申しました「素直さをもって曲に接する」ことそれが笛の要諦だと思うのです。
笛は人類の最古の楽器といわれています。縄文時代の遺跡からは石笛が発掘されこれは文字どおり石でできた笛です。石に人工的に孔を開けたのか雨だれなどによって自然に孔が開いたのかそこのところははっきりしないのですがとにかく石に孔が開いており今日の笛の原型になるものだと伝えられています。
竹の中に、特に女竹(通称、篠竹)と呼ばれる竹があります。節と節の間がスラリと伸びた細くて華奢な、その名のとおり美しい竹です。
篠笛はこの篠竹に孔を開けて管の内側に漆を塗っただけの簡単な笛です。竹の香が匂うような、素朴で柔らかい音色が特徴です。
昔はそれを単に「竹笛」と呼んでいたのですが私の父が「篠笛」という呼称を使いはじめたらいつの間にかそれが定着してしまいました。
この篠笛は平安時代にはもっぱら「田楽」の中で使われていたといいます。今日、これが篠笛のルーツとする説が有力です。
田楽とは当時の農村で田植えなどの農耕儀礼に笛や鼓を鳴らしながら唄い舞った田遊びでつまり初期の頃の篠笛は一種の村祭の楽しみといいますか地域社会の楽しみのために吹いていたのです。
それが後に専門の田楽法師といった専門の芸能家もあらわれ鎌倉時代から南北朝にかけては猿楽と同様に能管により能をも演ずるようになりました。
そしてしだいに中央にも伝わり鎌倉時代、室町時代以降になりますと町や都市に普及し洗練の度をまして市民の遊芸としてひろく行われるようになりました。
こうした成り行きの中で「篠笛」は常に主要楽器としての命脈を保ちつづけやがて「御神楽」「祭囃子」「獅子舞」などの中に採用されることを経最終的に江戸時代の中期歌舞伎の下座音楽と結びつくことによってその地位を不動のものとしたのです。
日本音楽の中で「竹」が果たしている役割は非常に大きいといえます。雅楽で用いる笛も、能管も、さらには尺八なども素材は竹です。
芝居や日本舞踊で使う鶯笛、虫笛などの特殊な擬音笛も含むと横笛、縦笛合わせて竹で作られた笛の数は枚挙にいとまがありません。
竹は根に近い方が太く、先へ伸びるほど細くなっていきます。それもただのまっすぐな筒ではなく、自然に曲線を描いている。
その内形が笛にとっては理想的なのだとある若い笛師が眼を輝かせて話をしてくれたことがあります。
フルートなどの金属楽器では”曲線”を作りだすのに大変な苦労をするそうです。
そういう事実を聞くと竹は笛になるべく生まれてきたような気がします。
天然の素材を活かしきったところに先人たちの深い智慧を感じずにはおれません。
竹という素材の素晴らしさは「形状」だけではなく古くなればなるほど音に深みが増すところにもあります。
漆を塗るのは虫喰いを防ぎ音質に柔らかさを出すためです。漆というのは乾燥しているところでは乾きにくく湿気のあるところでのみ乾くという不思議な塗料です。
そのため多くの職人さんは六、七月の梅雨時に集中的に笛づくりに励むようですが乾いた後、漆がおちつくまでには、さらに相当の歳月がかかります。
古い笛ほどいい音が出る理由は、ひとつにはこの事情によると思われます。何にせよ、「漆と竹の調和」なくして”笛の魅力”はありえません。
一般に、湿気は楽器にとって”敵”であるといわれ時に和製楽器ではそうした傾向が顕著のようですがことに笛に関しては逆で漆を塗った管の中が息を入れることによって湿気をともなってこないと好い音がしません。
竹というのは女性の肌のようにデリケートなもので置き場所も慎重になります。
笛にとってよくないのは極端に乾燥した場所、極端に寒い場所さらに直射日光が当る場所などです。こうしたところに長時間放置しておくとひび割れしたり、ひび割れしないまでも音質が悪くなります。
ストーブの真上だとか、冷房のききすぎた部屋などはいちばん置いてはいけない場所といえます。
最近はどこの会場にもエアコンが入り真夏でもしのぎやすくていいことはいいのですが笛の鳴りは悪くなりました。
エアコンの除湿機能が笛の湿気を奪いとるのでしょう。どうかすると笛の音にカサカサとかわいた雑音が入ります。
時たま汗だくになって吹いていた頃が懐かしくなり昔みたいに自然な環境で吹きたいと思ったりします。
私は本番前にすべて手孔を押さえ歌口から息を吹き込んで予め管内を湿らせておきます。
また、冬期は手のひらのぬくもりで笛を温めておいたりします。
「こういう時代だからこそこうした準備」がより大切になってきたといえます。いったん自分が手にした笛をいたわるのはプロ、アマを問わず笛に対する最低の礼儀ではないでしょうか。
ごくたまにですが古道具屋さんで製作から二百年以上経っていると思われる古い笛に出逢うことがあります。
そんなとき私は待ちこがれていた恋人にめぐり会えたような胸のときめきを感じます。古い笛を買ってきても、すぐにいい音が出るとは限りません。
むしろ出ないことの方が多いのです。音が全然出ないこともあります。しかし半年も吹いていると、ちゃんときれいな音がしてきます。
まるで二、三百年の昔から甦ったような、そんな素晴らしい音です。
笛というのはもともと、吹き込んではじめて良い音が出るのが特徴です。その意味では毎日、休みなく吹くことが最良の手入れ方法といえます。
笛は、楽器を演奏するというよりは竹に生命を吹き込むといった表現の方がぴったりします。
一年、十年、百年と、吹きこめば吹きこむほど丸みを帯びた柔らかく美しい音が出るようになります。
吹きこんだ笛というのは手離しがたく、愛しいものです。
単に愛着が湧くといったものではなく実際われわれと笛との結びつきはもう少し強いものであるような気がします。
そしてその想いは同じらしく竹に感情が出てくるのが不思議です。民俗学的には笛が男性で、太鼓が女性なのだそうです。
しかし、「女竹」のイメージが強いせいでしょうか私には笛はどうも女性特有の感情を持っているように思えます。
「夜泣きの笛」
の話をご存知でしょうか。持ち主があまり吹いてくれないのをさびしがった笛がひとりで夜中に泣くように鳴り出すという話ですが毎日笛と苦楽をともにしている私には素直に信じられる話です。
吹きこめば吹きこむほどいい音がしてくるのが笛の特徴だとすると新管と古管のどちらがプロの持ち物としてふさわしいか、答は明らかです。
現在、私が舞台で使っている笛の多くは三百年から二百年前の竹を素材にしています。
室町時代から江戸初期につくられた笛も何本か持っていますが中に「大雷神」と銘打たれた能管がありこれは少なくとも五百年以上前に製作されたと推測されています。
明和年間に福井松平家に所蔵されていたという由緒ある笛で私も家宝のように大切にしているのですが以前一度、内側の漆が剥がれてしまったことがあります。
そこから息の露が入ると竹が腐ってしまうのでやむなく専門の方に頼んで中を塗り重ねてもらいました。
音色が変ってしまうのではと、非常に心配しましたが手元に戻ってきた笛は前と変らぬ古管の音色で安心いたしました。
古管の奏でる音には、一切の淀みがなくいわゆる”研ぎ澄まされた音”がします。
新しい笛は気づくか気づかないか程度の「シャー」という雑音を発するのに対し何百年の歴史を持つ笛からは麗々しい透きとおった音のみが生じるのです。
私が究極的に目ざしている笛の境地は「自然法爾」あるがままの己の自然体であるがままに吹きしかもそれがおのずから寸分の隙も聴き手に感じとらせないような「隙のない芸」にまで完成されたものであることです。
笛の音は私自身の心の響きです。素朴な中に哀愁の溢れた竹の香り竹の肌の艶やかさまろやかさ風が吹いても雪が降りかかっても折れそうで折れない柔軟性のある芯の強さそして何よりも竹のようにまっすぐな心こうしたもの全てを私の魂として笛の音に託していきたいと思います。