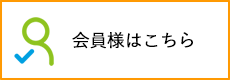玄信流 篠笛、横笛教室 八王子「竹の音會」は東京八王子、立川、多摩、日野近くでのレッスン、出張レッスンを行っております。オンラインレッスンもございます。
寒竹の笛
寒竹の笛
むかし、京都に永秀という風変わりな法師がおりました。
ひどく貧乏でしたがそれをいっこうに苦にせず日夜笛を吹いて暮らしていました。
その笛の音というのがたいそう美しくて近所の人々はうっとりして仕事が手につかなくなってしまいます。
そのために、一人去り二人去りしていつの間にかあたりには誰も住まなくなっていたほどでした。
さて、この永秀の親戚に石清水八幡宮の別当をつとめる頼清という人がいました。
ある時、頼清は永秀の貧乏ぶりをきき気の毒になって手紙を出しました。
「私の所にはいろんな人が相談に来ます。
それでお世話することが多いのですがあなたと私は親戚なのですから遠慮せず何なりとおっしゃってください。力になりましょう」
するとすぐに永秀の返事が返ってきました。
「ご親切ありがとうございます。さっそくうかがいます」これを見て、頼清はひそかに思いました。
「よけいなことをいったかなとんでもない要求されたりしないだろうな」数日後、永秀がやってきていいました。
「お言葉に甘えて参りました。ぜひ、お願いしたいことがございました」
金か、領地か、地位か・・・
頼清ははらはらして次の言葉を待ちました。
「あなたは筑紫の国に広大な領地をお持ちと聞いております」領地か・・・
「かの地には極上の寒竹が自生しているとのこと。
その寒竹を取り寄せてはいただけないでしょうか。
すばらしい笛ができると思うのです」「竹を・・・たったそれだけですか」
「はい、長年の望みなのです」頼清はあぜんとし感動さえおぼえていました。
「そんなことたやすいことです。
すぐにも取り寄せましょう。それより暮らし向きのことで何かありませんか。
お金とか物とか・・・」すると、永秀はにこにこしていいました。
「その点の心配は全く無用です。
春に着物一枚用意すれば秋までそれで充分ですし朝夕の食事はぜいたくをしなければどうにでもなるのですから」
頼清はいっそう感動しどこかで貧乏な永秀を馬鹿にしていた自分を恥じました。
真の風流人とはこんな人をいうのだろう・・・
頼清はすぐに極上の寒竹を取り寄せ永秀に送ったのでした。
とはいえ、かすみを食って生きるわけにはいかぬだろう。
頼清ははそう考え、時々生活に必要なお金を送り届けました。
すると、永秀はそのお金で酒や食べ物を買い石清水八幡宮の楽人を呼び集めてすべてふるまい連日かれらと合奏を楽しみました。
そして、お金がなくなるとまた貧しい暮らしにもどり相変わらず一人で笛を吹きつづけたのでした。
こうして永秀はいつのまにか二人といない笛の名手になったということです。